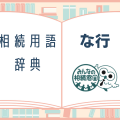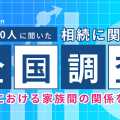認知とは?
相続手続きにおいて、子は第1順位の相続人ですが、一口に「子」と言っても、実子など違いが存在し、戸籍への記載方法や考え方が異なります。ここでは、認知について解説します。
認知とは
認知とは、法律上の婚姻関係によらず生まれた子(非嫡出子)を実子(血縁関係のある子)と認める行為をいいます。
民法第779条により、「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる」と定められています。
非嫡出子(婚姻関係にない父母の間に生まれた子)の法律上の親子関係は、父の認知によって成立します。民法第779条では母の認知も必要であると定められていますが、母には分娩の事実があるため、原則として母の認知は不要とされています。(※母が認知対象となる子は「捨て子」や「迷い子」です。)
認知の方法
認知は、認知届、遺言によって行うことができます(民法第781条)。
民法第784条により「認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる」とされています。そのため、仮に遺産分割が完了した後に認知された場合でも、さかのぼって相続権が発生しますので、認知された子は法定相続分に応じた価額の支払請求を行うことが可能になります。
The following two tabs change content below.


最新記事 by みんなの 相続窓口Ⓡ (全て見る)
- 相続工学というデータ研究を始めて5回目の春 元知事から「そこに愛」を求められた話 - 2025年5月2日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表最終回】親の死による相続の際、ペットが遺されたのは18%以上次の相続でペットが遺される可能性は16%以上~親族の集まる夏休みにペットと相続について考える~ - 2024年8月8日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第4弾】故人が営んでいた事業の10%超が廃業に~7/20中小企業の日を前に、事業とその承継に関するデータを公開~ - 2024年7月12日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第3弾】故人の1割近くが認知症 うち9割が終活での対策なし~6/14認知症予防の日を前に「終活」に関するデータを公開~ - 2024年6月4日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第2弾】相続人が不仲だと、紛糾リスクは約3倍 ~母の日を前に「相続における家族間の関係」を分析~ - 2024年5月1日
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。