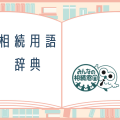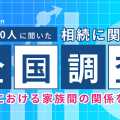寄与分と特別寄与料とは?
相続財産を受け取ることのできる相続人は民法にて定められており、また、その相続分についても目安としての法定相続分が民法によって定められています。しかし、亡くなられた方の生前に献身的な介護を行っていた方がいた場合、その方の相続分が他の相続人と同じであったり、その方が相続人ではなく何も受け取ることができなかったりしたらどうでしょう。ここでは寄与分と特別寄与料についてご説明します。
寄与分とは
寄与分とは、相続人の中に亡くなられた方の財産の維持又は増加について特別の寄与(貢献)をした人がいた場合、寄与した相続人に相続分以上の財産を取得させる制度をいいます。
ただし、この寄与分には注意が必要です。「相続人にしか認められていない」という問題があり、遺産分割協議の際に本人が主張し、相続人全員が合意することで成立します。合意が得られず協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。調停・審判へと進んだ場合、判断は家庭裁判所を通してなされることとなり、主張を行う相続人は、「自分の行為が特別の寄与であること」と「その行為によって亡くなった方の財産が維持若しくは増加したこと」を証拠で示さなくてはなりません。
寄与分とは(民法第904条の2)
・相続人の中に亡くなられた方の財産の維持又は増加について特別の寄与(貢献)をした人がいた場合、寄与した相続人に相続分以上の財産を取得させる制度です。
・寄与分は、相続人にしか認められていません。
特別寄与料とは?
寄与分には「相続人にしか認められていない」という大きな問題があります。例えば、夫の両親を介護した妻の場合、夫の両親が被相続人となっても、子の配偶者である妻は相続人ではありません。
特別寄与料では「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族」が寄与を主張することができます。寄与料請求権が認められるための要件は、以下のとおりとなっています。
特別寄与料とは(民法第1050条)
・被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族が寄与を主張することができます。
特別寄与料が認められる要件
①親族であること
②「自分の行為が特別の寄与であること」と「その行為によって被相続人の財産が維持若しくは増加した」こと
②の主張についての協議は寄与分同様まずは当事者間で行い、協議がまとまらなければ家庭裁判所に申立て、となります。特別の寄与についての証明が難しく、主張が認められることは簡単ではないという点は寄与分と同様です。
更に、特別寄与料についての申立て期限は「相続があったことや相続人を知ってから6カ月以内」か「相続開始から1年以内」とかなり短く設定されています。早急な対応が必要となるため気を付けましょう。
最新記事 by みんなの 相続窓口Ⓡ (全て見る)
- 相続工学というデータ研究を始めて5回目の春 元知事から「そこに愛」を求められた話 - 2025年5月2日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表最終回】親の死による相続の際、ペットが遺されたのは18%以上次の相続でペットが遺される可能性は16%以上~親族の集まる夏休みにペットと相続について考える~ - 2024年8月8日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第4弾】故人が営んでいた事業の10%超が廃業に~7/20中小企業の日を前に、事業とその承継に関するデータを公開~ - 2024年7月12日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第3弾】故人の1割近くが認知症 うち9割が終活での対策なし~6/14認知症予防の日を前に「終活」に関するデータを公開~ - 2024年6月4日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第2弾】相続人が不仲だと、紛糾リスクは約3倍 ~母の日を前に「相続における家族間の関係」を分析~ - 2024年5月1日
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。